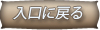【お題:なし 文字数:22,056字】
-都会の駅
ざわわざわ……ざわざわ……
今日も今日とて駅は混みあっていた。
サラリーマン、掃除のおばちゃん、学生、主婦……色んな人達が歩いている。
そんな人の波が細い駅の構内にひしめき押し合い、複雑な流れを作り出している。
最初に見たときは目を疑ったこの光景も、今となっては私の日常でしかなかった。
ボーっとした頭でそんなとりとめもないことを考える。
くだびれたワイシャツに、同じくくたびれたズボンに、
あまり見た目を気にしていないのが一目で分かるボサボサの短髪。
手には使い古された仕事用かばんが一つだけ……
そんな男がホームの隅っこで壁に寄りかかっていたところで、誰も気にすらしない。
目まぐるしく眼前の光景が変わり続けるのを見ながら、私はボーっとしていた。
ドーンッ!!
唐突に何かがぶつかる大きな音が聞こえ、
それと同時に足元に大小様々の物が転がってくる。
私はその音に吃驚して思わずカバンを床に落してしまった。
周りの人たちもその足を止めて何事かと辺りを見回している。
どうやら近くで掃除のおばちゃんがゴミカートをひっくり返してしまったようだ。
そこ中にゴミが散乱しており、なかなか壮絶な光景が生まれている。
おばちゃんは、私や周りの人にペコペコと頭を下げながらゴミを拾い集めている。
そんな光景をチラチラと見ながら、私は落したカバンを拾い上げようとする。
バサバサバサッ!
その瞬間、これまた大きな音を立ててカバンの中身が床へぶちまけられた。
しまった、落した拍子に留め金が外れていたのか……!
私は慌てて腰を落し、カバンの中身を拾い集める。
書類、メモ帳、スケジュール帳、名刺入れ、それと少し遠くに落ちていた古い御守り。
私はなるべく早くそれらを集めてカバンに入れなおし、そっと辺りを伺う。
サラリーマンや主婦、学生達や少女が何事もなかったかのように歩いている。
二回目だからだろうか、特に誰も気にしていようだったので私はホッと安堵の息をつく。
立ち上がろうと目を上げると少女と目があった、気がした。
私は慌てて目を伏せると、さっさと移動することにした。
やって来たのは先程に比べるとやや人の少ない古いホーム。
看板には大きく「22」と書かれている。
無意識に移動してしまったが、どうやら目的の場所に辿りついてしまったようだ。
人が少ないとはいえホームの座椅子は全て埋まっているし、
先程まで居た場所とはちがって寄りかかれるような柱も既に占拠されていた。
私は仕方なくカバンを床に下ろし、立ちながら電車が来るのを待つことにした。
私がいまから向かおうとしているのは実家のある山村である。
ここ数年仕事で忙しかったために実家へ顔を出すことができなかったのだが、
つい最近大きなプロジェクトが一段落して余裕が生まれたので、
こうして久しぶりに実家へ帰ることにしたのだ。
……まあ、もうひとつ別の理由があったりもすけど、ね。
しかし、時期は8月の中旬。
見事にお盆の時期と重なってしまい、帰省ラッシュに巻き込まれてしまった。
辺りを見回してみると、やはり多いのは家族連れだろうか。
はしゃぎ回る子供たちを何とか落ち着けようと苦心しているのが見て取れる。
ほかにも年若いカップルや、スーツを着たサラリーマン達。
雑談に花を咲かせるご婦人方や、
大きなバックパックを背負った外国人の集団もみえる。
それにアレは……小学生達と先生が一人か。
ユニフォームを着ているところを見るに、おそらく何かの合宿か遠征の帰りなのだろう。
引率の先生がざわめく学生たちを必死の形相でまとめようとしている。
あ、男の子が首根っこ引っ掴まれて引きずられている。
ガキ大将的な位置にいるのか、取り巻きが先生に文句をぶーたれてる。
男の子の視線の先には……ああ、成程。
帰省しようとしている女の子にちょっかいをかけてたのか。
相手の女の子は……白いワンピースに黒髪が似合っている。
って、私は何をまじまじと見ているんだ……
相手に気付かれる前に視線を逸らす。
私が小学生だった時とそんなに変わっていないんだな。
私はなんだか懐かしい気持ちになってきた。
小学校の頃の私は大人しい子だった。
クラスのガキ大将的な子達が騒ぐのを離れていたところから関わらないようにしていたし、
そのせいでよくガキ大将グループからちょっかいをかけられたものだ。
お陰で男子グループとはそんなに遊んでなかったんだよなぁ……
それでいて女子グループとも中々話せなかったので、必然とクラスからは孤立していた。
唯一話せたのは家の近所の神社に住んでいた幼馴染のあいつぐらいだったか。
つい先日声を聞いた限りでは昔と変わらず元気いっぱいという感じであった。
あいつは本当に小学校の頃から変わらないよなー……
小学生達の姿を見て思わず古い記憶を引っ張り出して思い出に浸っていると、
ホームに新幹線の到着を知らせる騒々しいアナウンスが響き渡る。
その音に一瞬ビクッと身を竦ませるが、それも一瞬のこと。
私は思い出にそっと蓋を被せると、アナウンスに従って新幹線に乗り込んだ。
―電車の中
『次は終点○○駅。お降りの際は忘れ物がないか確認してからお降りください。』
新幹線に乗り込み約3時間、ようやく地元に帰ってきた。
とはいえ私の実家へ向かうにはこの駅で地方鉄道に乗り換えなければいけない。
新幹線内を見回してみるが車内にはまだまだたくさんの人達が乗っている。
しかし3時間も経てば誰だって疲れるもので、
駅のホームの時ほどの賑やかさはもうない。
まあ、なんにせよこの過密地帯から抜け出せるのならばなんでもいい。
私は荷台に上げていた荷物を降ろし、新幹線の降り口へ向かった。
決壊した堤防から溢れ出る水のように、
出口から降りていく乗客たちに紛れて新幹線を降りる。
ホームを少し歩いて人の少ない場所へ行くと、荷物を床に降ろして一息ついた。
やれやれ、帰省ラッシュがここまでハードなものだとは知らなかった。
私は荷物の中から飲み物を取り出して、一気に飲み干す。
ああ、生き返る……
とはいえここでのんびりしていては次の電車を逃すかもしれない。
私は気合を入れなおして荷物を肩にかけ直し、
地方鉄道が走っているホームへと移動する。
歩きながら駅内を見回してみると、見たことのないお店や建物が目に入る。
数年帰らなかっただけでこんなにも変わるものなのか……
そんなちょっとした変化から時の流れを感じてしまう。
気付けば私は足を止めて辺りを見回していた。
あそこの立ち食い蕎麦屋、相変わらずスーツ姿のサラリーマンばっかりだ。
おかげで食べたのってほんの数回ぐらいしかないんだよなあ。
その隣の喫茶店は今でも学生たちの溜り場になっている。
私の通っていた高校の学生服を来た男女のグループや、
近隣高校の学生服を着た男子学生たちが大勢たむろしている様子が見える。
待ち合わせ場所によく使われていた時計は新しくなったみたいだ。
ここを最後に使ったのは、大学に出る時に幼馴染と待ち合わせをした時だったっけ。
ポトッ
そんな風に考え事をしていたせいで御守りを落としてしまった。
そういえば、この御守り……
私は拾い上げた御守りの口をそっと開ける。
中には紙に包まれた小さなリングと、折りたたまれた紙が一枚。
この紙は……大学へ行く日に渡せなかったラブレター。
あの日、お互いに何か言おうと思って、でも結局どちらも言えなかった。
あの時、もっと勇気があれば別の未来もあったのかもしれないな……
ははっ、未練たらたらじゃないか……もう、終わったことなのに。
自分の未練に渇いた笑い声を上げ、私は御守りの口を閉じた。
御守りを荷物の中に仕舞い込み、ふと時計の文字盤に目を向ける。
うわ、もうこんな時間か!?
そろそろ電車が来る時間だったはず。
私は頭を一振りして感傷を振り払うと、地方鉄道のホームへ向かって歩き始めた。
地方鉄道のホームについた私は、すぐさま時刻表を確認する。
……よかった、間に合ったみたいだ。
この地方鉄道は利用者が少ないため極端に本数が少ない。
朝や夕方の通勤時には1時間に2,3本走ることもあるが、
それ以外の時間では1時間に1本。酷い時には2時間に1本しか走っていない。
結構待つことになるんじゃないかと覚悟していた私は、思わず安堵のため息を漏らした。
ホッと一息つけたことで心に余裕が生まれたので軽く辺りを見回してみる。
昼前だというのに地方鉄道のホームにはまばらにしか人がいない。
手に荷物を持ったお年寄りや、小さい子供を抱えたお母さん。
麦わら帽子を被って、しきりに窓を見ている女の子もいる。
あとは地元の大学生っぽい連中がグループで来ているぐらいか。
そんな懐かしい光景を眺めていると、電車がゆっくりとホームに入ってきた。
私は床に降ろしていた荷物を持ち直し、
記憶の中の姿よりも一回り古くなったように見える電車に乗り込んだ。
乗り込んだ車両の中には誰も乗ってなくて、ガラガラだった。
ホームにいた他の乗客は、別の車両に行ってしまったみたいだ。
私は意図せず貸切となってしまった電車の中を見回す。
ガラガラの座席のどこに座ろうかと悩んだが、
悩む程のものではないかと思い直して車両中央のボックス席に座る。
荷物を横の席に置き、誰も座っていない対面の席を見ること数分。
結局車両に誰も入ってこないまま、電車はゆるゆると動き始めた。
流石に暇だったので私は車窓から外の景色を見ることにした。
電車が走り始めてしばらくはビル等の建物もチラホラ見えていたが、
2駅過ぎた辺りからは建物は少なくなり、
4駅過ぎた頃には田園とその中にポツポツと建っている民家しか見えなくなる。
そんな懐かしい風景に見とれていたからだろうか。
ふと視線を電車の中に戻した私は、対面の席に座っていた少女を見てびっくりした。
「あはっ、やっと気付いた」
少女は驚いて固まる私を見てコロコロと笑い出す。
最初こそ驚いたものの笑い転げる少女を見ているうちに、少し落ち着いてきた。
少女の年は10歳ほどだろうか。
白いワンピースに、腰まである長い黒髪がよく似合っている。
少女が座っている席の隣には大きな麦わら帽子と手提げ鞄。
どうやら何処かへお出かけした帰りのようだ。
「ね、ね。おにーさんどっからきたの?」
少女はそのクリクリとした瞳をこちらに向け、元気に溢れた声で質問を飛ばしてくる。
久々に聞いた田舎独特の遠慮のなさに苦笑しつつ私は答えを返す。
「おー、都会だねー!」
そ、そんなに驚くことかな。
色々気になる年頃だからなのか、しばらく少女からの質問が続く。
その質問に答えるたびに少女は「へー」とか「凄い!」とか反応を返してくる。
うーん、ちょっと楽しくなってきたぞ。
そんなやり取りがしばらく続いた後、
少女はピタッと質問をやめるとズイと私の方へと体を乗り出してきた。
「んーと?」
その少女の行動に再び驚いた私は身を固くするが、
少女はそんなことお構いなしに私の荷物にとりつこうとするのを見て、
私は慌てて荷物を手元に引き寄せる。
「ちょっと、ちょっと見せてってばー」
少女はそう言って荷物を引っ張る。
しばらく無言で引っ張り合いをしていたが、
やがて私は根負けして少女に荷物を手渡した。
「あー、やっぱりー!」
荷物のポケットをゴソゴソと弄っていた少女が唐突に叫ぶ。
その手にはボロボロになった御守りが一つ。
ありゃ、そんな所に仕舞っていたのか。
その御守りは家の近くの神社で売っていたもので、縁を繋ぐ御守りらしい。
「ねえねえ、この御守りっておにーさんのだよね?」
ボロボロになった御守りの表面を優しく撫ぜながら少女が聞いてくる。
その質問に私は顔を縦に振って答える。
すると少女はじーっと御守りを見つめた後、
足をバタバタさせながら興奮気味に聞いてきた。
「もしかしておにーさんって神社の近くに住んでる?」
!?
この質問に私はとてもびっくりした。
確かに私の実家は神社の近くにある。
この神社には毎年必ず家族そろって新年の挨拶に行っているし、
私にとっては非常に馴染みの深い神社である。
しかし御守りを見ただけでそこまで分かるもんなのか……?
「あはははっ、やっぱりそうなんだ」
目を見開いた私の様子から、自分の推測が正しかったと確信したのだろう。
少女はその愛くるしい顔に誇らしそうな表情を浮かべる。
いや、しかし、どうして分かったんだ。
私の頭の中で疑問がグルグルと渦巻く。
むっつりと押し黙って自分の考えに没頭してしまった私だったが、
黙ってしまった私を見て少女は私が怒ったのだと考えたようだ。
誇らしそうな表情を引っ込め、叱られた子供のように目を俯かせる。
ああ、そんなつもりじゃなかったんだけども……
私がどうしたらいいか分からずに困っていると、
少女はチラチラと上目遣いでこちらの表情を伺いながら喋りだした。
「えっとね、その、わたし、実はその神社に住んでるの」
「だから、その御守りにも見覚えがあったし……」
「お兄さんのことも見たことあるような気がして……ホントにホントだよ!」
少女が「信じて!」と真剣な目で訴えかけてくる。
元から疑っていたわけではないんだけどなあ……
ああ、でも、なるほど。この子は神主さんとこの娘さんだったのか。
疑問が氷解した私は少女にニッコリと笑顔で微笑み、
怒っていないことを手振りと表情で伝える。
少女は最初「ホントに……?」という顔をしていたが、
私が本当に怒っていないことを察すると再び笑顔になった。
「えへへ、おにーさんが怒ったのかと思ってびっくりしちゃったよ」
少女はさっきまでの様子が嘘のように笑顔になる。
うーん、子供はやっぱり切り替えが早い。
その様子に私は苦笑する。
そんな風に少女とやり取りを繰り返していると、
唐突に車内のスピーカーから「ザーッ……」という雑音が流れ出した。
『えー……間もなく△△ー、△△に到着しまーす。
お降りの際は列車とホームの隙間に気を付けてくださーい』
少女と盛り上がっているうちに目的の駅に到着したようだ。
「お兄さんもここで降りるんでしょ?」
ああそうだよと私は頷き、降り逃さないように荷物をまとめ始める。
少女も横に置いてあった麦わら帽子を被りなおし、勢いよく立ちあがる。
少女に続くように私も荷物をまとめあげ、席を立った。
「おにーさーん、早く早く!」
少女は電車内を駆けまわりながら私を急かしてくる。
その光景を微笑ましく眺めているうちに、電車が駅のホームに停車する。
少女は最後にもう一度「はやくー!」と言うやいなや降り口へ走っていく。
私は最後に忘れ物がないことを確認してから、少女に続いて駅に降り立った。
―地元の駅
駅に降りた俺は鞄を一度地面に置くと、大きく伸びをする。
椅子に座り続けたせいで凝り固まった身体から、ポキポキと小気味よい音が鳴る。
最後に首をコキコキと左右に振る……ああー、スッキリした。
そんな風にダラダラしていたが、少女がじぃっと見ていることに気付く。
……妙に恥ずかしくなった俺は鞄を持ちなおすと改札口へと歩き出す。
「あ、ちょっと!」と言う少女の声が誰も居ないホームに響き渡るが、
俺は真っ赤な顔を見せまいと改札口へと歩いて行く。
この駅は村に一つしかない公共交通機関だ。
うちの村にはバスが来ないので、必然的に村の住民はこの電車を利用することになる。
しかし学生以外の住人があまり村の外へ出ないため、
朝と夕方の通学ラッシュ以外は常にガランとしている。
そのため、この駅は駅員の居ない「無人駅」となっている。
俺は静かなホームを少し急ぎ足で歩き去る。
改札口の切符入れに切符を放り込み、改札を抜けた所で立ち止まる。
後ろを振り向くと、丁度少女が改札口を通り抜けるところだった。
少女は自分を見ている俺の視線に気付くとブーブーと不満を訴えてきた。
「ひっどーい、なんで置いてくの!」
まさか「恥ずかしかったから……」なんて素直に言えるわけもなく、
曖昧な笑顔でお茶を濁して明後日の方向を向く。
やはりというか、少女はムスーっとしたままだ。
はぁ、どうしたもんかな。
などと思っていた俺だったが、ふとある事を思い出して鞄を漁り始めた。
んー、確か部活用に買ってた奴がこの辺にあったはずなんだけど……
ゴソゴソと鞄を漁り始めた俺を怪訝な目で見ている少女だったが、
俺がチラッと目を向けるとフイ……と視線を逸らしてワンピースを弄り始める。
それでも興味はあるのか、ときどきチラチラとこちらを見ているのが丸わかりだ。
そんな少女の仕草を見て苦笑をこぼしつつゴソゴソやっていると、
ようやく目的のモノを探し当てる。
取り出した拍子に帽子やら御守りが落ちてしまったが……まぁ良いや。
それらはとりあえずズボンの後ろポケットに突っ込み、
俺は取り出したソレを少女に向かってヒョイと差し出した。
「むー……ん??」
最初は怪訝な顔をしていた少女だったが、
差し出されたソレの正体に気付くと途端に笑顔になる。
「ねえねえ、これ食べていいの!?」
俺は何もいわずにもう一度差し出す。
「やったー!」
少女は歓声を上げて俺の手からソレが入った袋をかっさらい、
いただきますと言うやいなや俺の目の前でパクパクと頬張り始める。
こいつ、少しも遠慮しねえんだな。
その様子を苦笑交じりの笑みを浮かべながら見ていると、
少女はピタっと止めて手足をバタバタさせ始めた。
「ん、んふーっ!ふまっはー!」
口いっぱいに頬張っていたせいで何を言っているのかさっぱり聞こえないが、
それでも必死のジェスチャーから何が欲しいのかは分かった。
俺は笑みを噛み殺しながら再び鞄を漁る。
「〜〜〜!〜〜〜!!」
いよいよ切羽詰ってきたのだろうか、声も出さずに俺の背中をバシバシと叩き始める。
今探してるんだから落ち着け……ってのは無理な相談か。
俺は少し急いで鞄の中を漁り、ようやく目的のものを見つける。
俺が水筒を少女に差し出すと、少女は蓋を開けてゴクゴクと勢いよく飲み始めた。
「ふはーっ!! ありがとー、死ぬかと思った」
それだけ言うと、少女は再び食べるのに夢中になる。
口の周りに食べカスが尽いているのにも気付かずに食べ続ける少女に、
なぜか俺は自分の子供時代を重ねていた。
少女が食べていたのは何の変哲もない「どら焼き」だ。
別に有名店で買ってきたとかそういうわけでもない、
コンビニに行けばいくらでも売っているやっすいお菓子。
でも、この辺りじゃお祝いごとの時にだけ食べられる特別なお菓子だったりする。
俺も他町の高校に通い始めてコンビニで見かけるまでは、
特別なお菓子なんだと本気で思ってたんだよなぁ……
まあ、そういう理由もあってこの辺りの子供はどら焼きには目がない。
もちろん俺もその例に漏れずどら焼きが好きだから、
ストックが切れる度に高校近くのコンビニで買い足していたりする。
昔は幼馴染の家に行けば貰えたんだけどなー……
残念ながら高校に上がってからは幼馴染と疎遠になってしまったので、
昔のように神社にお邪魔して一緒に食べるなんて真似はできないのだけれども。
別に喧嘩したとかそういう理由ではなく、なんとなくそうなってしまったのだ。
けれど、朝登校する時や休み時間にふとお互いの目が逢うことがあるし、
お互いなんとなく相手が気になっているのは確かなんだよなぁ。
友人からはさっさと告っちまえよと煽られるが、まだそんな気分にはなれない。
まぁ、まだ時間はあるし今すぐじゃなくても問題ないだろう。多分。
先日あった出来事を思い返して時間を潰そうとしたが、
テンションが下がってしまったので止めにする。
代わりに横でどら焼きを頬張っている少女に目を向ける。
少女は先程と同じようにガツガツ食べているが、
途中途中に休憩を挟んで喉につまらせないように気をつけて食べている。
少女の食べっぷりを見ているうちに俺も食べたくなってきたので、
ベンチに腰掛けながら鞄から取り出したどら焼きに齧り付く。
モグモグモグ……
やっぱり美味ぇなあ。
しばらくの間、二人黙々とどら焼きを食べる。
お腹が減っていたこともあり、俺はぺロリと平らげてしまった。
少女の方を見てみると、どうやら少女も食べ終えたようだ。
「ごちそうさま!」
ごっそさん。
少女の機嫌は元に戻ったようで再びニコニコと笑っている。
その少女の顔を見ていると、食べカスが頬に付いたままになっているのに気付く。
俺は指の背で少女の頬に付いた食べカスをヒョイッと取ってやる。
その行動に「ひゃわっ!」と変な声を上げるが、
俺の指に付いた食べカスに気付くと慌てて口周りをグシグシと拭き始めた。
「ね、もう付いてないかな?」
そう言って少女はグイッと俺に顔を近付けてくる。
この辺の子供にしては色白な肌にぷっくりとした唇。
さきほどまで興奮していたせいだろうか、頬には僅かに朱がさしている。
この顔を見ていると、不思議とドキドキするのは何故だろうか。
雑誌の美人モデルを見てドキドキするのとも、
クラスで一番可愛い子を見てドキドキするのともちがう。
なんだろう、まるで幼馴染を見ている時のような……
じっとその顔を見ながらそんな事を考えていた俺は、
少女の「どうしたの?」と言いたげな表情に気付いてハッとする。
なんでもないと身振りで示し、頭をブンブンと振る。
まったく、なに考えてるんだか……
少し落ち着いた俺は椅子から立ちあがり、
少女に向かってそろそろ行こうかと手を差し伸べる。
少女は俺のその手を握り締めて元気よく「うん!」と答え、
ピョンッと椅子から勢いよく立ちあがる。
そして手を握ったままそのまま駆け出し「はやく、はやくー!」と急かし始める。
その様子に毒気を抜かれた俺は鞄を持ちなおすと、
少女に手を引かれながら燦々と輝く日の下へと歩を進めた。
―人気のない帰り道
ジーワ、ジーワ、ジジジジ……
蝉の鳴く声が頭の中で反響する。
うっせぇ……
駅を出てそろそろ半刻。
真昼間のピークもうとっくに過ぎたというのに全然涼しくならねえ。
しかも駅から神社までの道は田んぼの中を突っ切って行くせいで、
太陽を遮ってくれるものが何もないという有様。
ジリジリと生き物全てを焼きつくそうとするかのような暑さに耐えられず、
オレはバックから水筒を取り出すと中身を一気に喉へ流し込む。
ゴク、ゴク、ゴクッ……
プハッ、あー生き返るー。
水筒と一緒に取り出したタオルで顔と首筋を拭う。
上着はとうの昔に脱いで腰に巻いている。
普段であれば真っ白な布地に泥が跳ねるのを嫌がってそんなことはしないのだが、
既にユニフォームは泥で汚れきっているから問題ない。
「〜♪〜♪」
となりからはご機嫌な鼻歌が聞こえてくる。
いや、なんで神社の神楽の時に流れる神楽歌なんだよ……
ツッコミを入れたくなってチラッと横目に見てみると、
微塵も暑さを感じていないような能天気な笑顔が目に入ってきた。
こいつ、疲れを知らねーのか……女の子ってのはタフなもんだなぁ。
いやでも思い返してみれば幼馴染もそうだったかもしれない。
小学生の頃はオレと一緒に野山を走り回って遊んでいたし。
まぁ中学生になってからはあんま遊ばなくなったけど、
朝連に行く途中で朝早くから神社の階段を掃除している姿を見かけるし、
部活が終わった後にふと神社に行ってみると何かの稽古に励んでいる姿を見る。
男のオレでもバテそうなスケジュールなのに、幼馴染は全然平気そうな顔をしていた。
男として悔しい半面、お陰でより一層練習に身が入ったんだけどな。
そんなことを暑さでボーっとなった頭で考える。
そんなオレを急かすようにグイグイと袖を引っ張る女の子。
「あんまりのんびりしてると日が隠れちゃうよー?」
まったくもう、こちとら練習で疲れてるんだから急かすんじゃねーよ……
もちろん心の中で愚痴るだけである。
というかこの子、幼馴染そっくりだなぁ。
容姿もそうだけど性格までそれっぽい。
このグイグイ引っ張って行く感じとか、こっちの都合を考えない感じとか。
まぁ、今となってはそんな事もねーんだけどな。
入学した当初は小学校のノリで一緒に遊びもしたし、
家に帰る時もいっつも一緒だったんだけど。
そのうちクラスメートからからかわれる様になっちゃって。
いやオレは全然気にしてなかったけど、
やいのやいのとからかわれてる幼馴染を見てるとなんか嫌でさ。
さっさと野球部に入部して部活を言い訳にして幼馴染と距離を開けた。
丁度幼馴染も家の手伝いが忙しくなって早めに帰るようになってたから、
自然と一緒に居る時間はなくなって、小学校の時みたいな関係じゃなくなった。
んー、丁度いい時期だったと思うよ。オレにとっても、幼馴染にとっても。
……ちょっと、寂しい気はするけどさ。
グイグイ、グイグイ……
「もう、また足が止まってる! 足を止めちゃ駄目だってー!」
女の子はオレの袖を引っ張って早く早くと急かしてくる。
おいおい、折角木陰ができてんだからもう少しゆっくりとだなぁ……
なんてことを思いながらガサガサとバックの中身を揺らしながら早足で歩く。
オレはその音を聞いて今日の昼の出来事を思い出した。
……今日の昼、俺は別のクラスの女子から告白された。
なんでも野球の練習をしている姿が格好良かったからだそうだ。
いや、正直びっくりしたね。
元々大人しくて幼馴染以外とは話したことなかったから。
まぁでも興味がないワケじゃないからその時は受けようと思ったんだけど……
なんでだろうなぁ、幼馴染の顔が浮かんできたんだよね。
その瞬間に興味なんてパッと失せちゃって断っちまったんだけど、
今考えなおすと絶対損したよなー、メッチャ可愛かったし。
はぁー……まぁ、いっか。またチャンスはあるでしょ。
そんなことを考えながらオレは女の子に手を引かれて歩いていく。
オレ達は田んぼの真ん中を突っ切っている農道を通り過ぎ、
今は鬱蒼と生い茂る木々に囲まれた山の小道を歩いていた。
さっきから女の子がオレの手を引っ張る力が強くなってきた気がする。
確かに木が生い茂って暗がりが出来るから怖い場所なのは分かるけどさ、
今はまだ明るいんだしそんなにビビる必要なんて……
ガサガサガサッ!
!?
な、なんだ、なにかいるのか!?
そんな風に考えていたせいで、突然鳴った物音にいつも以上に反応してしまった。
女の子も音に驚いたのか、オレの袖をより一層強く引っ張る。
「はやく、はやく!」
その声にハッとして茂みから目を逸らす。
目を逸らそうとした瞬間に赤く光るなにかが二つ見えたような……
オレは好奇心を抑えようとしたが、駄目だった。
手を引く女の子に気付かれないようにコッソリと暗がりに視線を向ける。
!?!!?
居たっ!?何か居た!
イノシシとか、鹿とかの獣とは明らかに違う。
あんな風に爛々と赤く目を輝かせる動物を、オレは知らない。
しかも、目があった……!
慌てて目を逸らしたけど、今でも見られている気がするっ……
ガサッ……ガサガサッ……
!!
お、追って来てる!?
その音が聞こえたからだろうか、女の子は走るスピードを上げる。
オレも必死になって女の子の後を追いかけた。
ちくしょう、いつも通ってるはずの小道が全然違って見えるぜ……
無我夢中で走っていたせいでオレは何度か山の奥へと入り込みそうになるが、
そのたびに女の子に手を引かれて元の小道へ戻る。
サワッ……
うひぃ!?
な、なんか首の辺りに変な感触がっ……って、枝かよ! 畜生!
ああくそっ、さっきからそんなのばっかだ!
もうちょっとっ、枝とか、葉っぱとか、落としてくれよ!
くっそ、また服が……外れろっての!
たびたび引っかかってつんのめりそうになるのを何とかこらえ、
オレと女の子はひたすら小道をかけ下りていく。
……ようやく山を抜けた時には、辺りは夕焼けの色で赤く染まっていた。
無我夢中で走っていたせいか、日が落ち始めていることに気が付かなかったみたいだ。
ああくそ、かっこ悪ぃな……
もう後ろから何も追ってきてないことを確認しながらそう思う。
「もう、お兄さんちゃんと真っすぐ走ってよ……」
女の子は木の根元に座りながらそう言葉を漏らす。
まったくもってその通りだ。
情けなさ過ぎて涙が出てきそうだよチクショウ。
恥ずかしさで女の子の顔をまともに見れなかったオレは来た道へ顔を向ける。
それにしてもあの音は結局何だったんだろうか。
オレが知ってる獣なんて爺ちゃんが取ってきたイノシシぐらいだけど、
でもあんな風に追っかけてくるなんて話聞いたことないぞ。
そもそも一度もまともに姿を見てないし……本当に獣だったのか?
それに……いや、オレの考えすぎかもしれないけど。
あの獣、なんだかオレばっかり狙ってたような気がする。
や、オレが女の子の後ろにいたせいかもしれないけどさ。
そこまで考えた所でブルリと俺の体に悪寒が走る。
止め止め、止めだ。考えたって仕方ない。
見ると既に日が山に落ちようとしていた。
そろそろ辺りも暗くなってくるだろう。
オレはともかく、女の子がそんな時間までウロウロしてるのはマズイ。
そう思ったオレは女の子に声をかけようと振り返る。
「ん、もう行く?」
女の子はそう言うと手をパッパッと打ち鳴らして立ち上がる。
木の根元で何か触っていたのかその手はやや汚れている。
オレはちょっと気になって女の子の後ろを覗いてみる。
何だあれ、でっかい石……いや、お地蔵さん?
オレが女の子の後ろをじーっと見つめているのに気付いたのだろう。
女の子はパンッ!と強く手を打ち鳴らしてオレの意識を自分に向けさせる。
「ほーら!行くならさっさと行こ! 追いてっちゃうよ!」
そう言うやいなや女の子はさっさと先に進んで行ってしまう。
お、おいおいちょっと待てよ!
女の子の後に続こうとしたオレだったが、ふと気になってもう一度背後を振り返る。
ゾクゾクゾクッ!
さっきとは比べ物にならない悪寒がオレの背中を襲う。
触らぬ神に祟りなしってヤツだ……!
オレは踵を返すと、女の子の後を追って走り出した。
―山奥の神社
カァー、カァー、カァ……
神社に着いたときには太陽が山に隠れはじめていて、
カラス達が鳴き声を上げながら山の方へ飛んでいくのが見えた。
ぼくは神社の鳥居を勢いよく走り抜けると、
後ろをついてきているあの子の方を振り返る。
けど、そこにあの子はいなかった。
早く走りすぎたかな……でもまあ、すぐ追いついてくるよね。
ぼくはあの子が来るまでの間、神社の中をぶらぶらして時間をつぶすことにした。
ぼくんとこの村の神社は小ぢんまりとしていてボロボロになりかけの神社だ。
鳥居なんてところどころの色が剥げてるし、狛犬には緑色のコケがビッチリ生えてる。
手を洗うところの水はチョロチョロっとしか出てなくて、飲もうって気にはなれない。
それでも境内はちゃんと綺麗にされていいて、ゴミとかぜんぜん落ちていない。
ここの神社の人がいっつも朝と夕方に掃除しているからだろうけど、
毎日掃除するって想像するだけでいやだ……よく毎日続けられるなぁ。
ガラガラガラッ……
そんな風に考えていたら神社の母屋の方から木の扉を開ける音が聞こえてきた。
誰だろうと思ってそちらの方を見てみると、
やや古ぼけた巫女装束を着ている20代後半ぐらいの女の人がいた。
あれ、誰だろう。見たことのない人だなあ。
ぼくの知ってる神社の人といえば、幼馴染のお婆ちゃんかお母さんぐらいだ。
じーっと見つめているうちに、女の人もこちらの視線に気付いたようだ。
辺りをキョロキョロと見回してからこちらを見て軽くうなずくと、
やや小走りにこちらへ歩いてきた。
「ひとり?」
女の人の問いにひとつ頷く。
すると女の人は一瞬だけ怖い顔をする。
「まったく、どこほっついてんのかしら……。
うーん、でも、まだ時間に余裕はあるし……」
そう言って何かを考え込み始める。
そういえば今って何時ぐらいなんだろう。
山に夕日が隠れ始めてるぐらいだから、夜の6時過ぎぐらいかな?
ぼくの家の夕食は半ぐらいからだから、まだ大丈夫なはず。
「もしかして気を利かせてくれたのかしら……」
そう零して女の人は、はぁ〜と大きくため息をつく。
ため息をついているはずなのに、その顔は少し嬉しそうだった。
「ごめんなさい、ちょっと掃除だけ済ませてしまうから」
そう言って女の人は手に持っていた箒で辺りを掃き始めた。
サッサッサ……
箒が乾いた石畳を掃く音が辺りに響き渡る。
長く伸びた女の人と箒の陰をじっと見ていたけど、すぐに飽きた。
長い階段を一気に走ってきて疲れていたぼくは、
座れるところを探して社の辺りをウロウロする。
フラフラしながらチラッと覗いた賽銭箱の中身は相変わらず空っぽだった。
ここに小石や葉っぱを入れて怒られたこともあったなあ。
あれは誰に怒られたんだっけ、幼馴染だったかな。
小さい女の子だったのは覚えているんだけどなー。
ガラン、ガランガラン
あれ、このガランガランするやつ新しくなった?
この前までぜんぜん鳴らなかったのになー。
調子に乗って何回もガランガランと鳴らしてみる。
「こらっ、何度も鳴らすな!」
女の人に注意された。ちぇー。
女の人は石畳を掃き終わって箒をしまうところだった。
箒をしまった女の人は桶と柄杓を手にとり、今度は裏山へ続く小道へ水をまき始めた。
雑草や小石が丁寧にどかされて綺麗な砂地になっていた小道が、水で清められていく。
なんとなくぼやーっと暗かったところが少し明るくなってて綺麗だなー。
ぼくはその光景を賽銭箱前の階段に座ってじっと見つめていた。
女の人が水をまき終わって片付け始める頃には、
太陽は山の向こうに半分ぐらい消えて辺りは真っ赤になっていた。
さっきまで頻繁に聞こえていたカラスの声もぱったりと止んで、
辺りには蛙の鳴き声が響き始めている。
掃除用具を片付けた女の人はいったん母屋に戻ると、
麦茶を入れたコップとどら焼きをお盆に乗せて戻ってきた。
「はい、お茶」
それだけ言ってお盆を床に置くと、女の人はさっさとお茶を飲み始めた。
ぼくも飲もうと思ったけど、ふとあることを思い出して手を引っ込める。
「あれ、いらないの?」
女の人はそんな風に聞いてきたので、コクリと頷く。
「そっか」
そう言って女の人は自分のコップに再び口をつける。
「ん〜、甘くて美味しい」
やっぱり。
この神社のお茶といえば砂糖入りの麦茶なんだよね。
甘いお茶は別に嫌いじゃないんだけど、
飲むとお腹が膨れるから夕飯前に飲んじゃ駄目ってお母さんに言われてるし……
そう思っているうちに女の人は飲み終わって、大きくグ〜っと伸びをしていた。
そのまま二人、特になにもせずにボーっと境内を見つめる。
そういえば、あの子は何処へ行ったんだろ。
神社に帰るって言ってたはずだから、母屋のほうに行ったのかな。
「ねえ」
そんな風に考えていると、女の人から声をかけられた。
その声はさっきまでの感じとはちがって、少し暗い感じがした。
「キミはさ、好きな人いる?」
ぼくはその言葉を聞いて一瞬だけ幼馴染の顔を頭に思い浮かべたけど、
ブンブンと頭を振ってその考えを忘れる。
「私はいる……ううん、いたんだ」
ぼくが黙っていると女の人は静かに喋りだした。
「小さい頃から仲良くてた男の子だったんだけどね、今は……遠くに行っちゃったんだ」
女の人の表情に少しだけ影が差す。
ぼくは黙って聞いていた。
「小さい頃の私はね、元気いっぱいな女の子だった。
逆にアイツは男のくせに静かで、大人しくて、まるで女の子みたいなヤツだったの」
女の子みたいって……まるでぼくみたいな子なんだなぁ。
ぼくも幼馴染からしょっちゅうそんな風に言われるし……
その度に悔しくて、悔しくて、もっと男の子っぽくなろうって思うけど。
「最初は家が近いからって理由で遊んでたんだけど、
小学校の高学年ぐらいからかな?
遊ぶ度にだんだん気になるようになってきたの。
その時はそれが何なのか全然気付いてなかったんだけどね……
自覚し始めたのは中学生の頃から。
小学校までは男らしくなかったアイツが野球部に入ってさ、
それまで運動はダメダメだったのにどんどん上手くなっていったの。
その頃からカッコ良くなり始めちゃってさ、結構モテてたのよ」
女の人はそこで少しだけ頬を膨らませる。
そんな子供っぽい仕草が妙に似合っていてぼくは思わず見とれてしまう。
女の人はそんな視線には気付かずに話を続ける。
「それでね、ある時告白されてる場面を見ちゃって……
その時に私気付いたんだ、アイツが好きなんだって。
それからかな、だんだん遊ばなくなっていったのは。
まあ、お互い学生生活が忙しかったからってのもあるんだけど。
高校に上がってからはクラスが同じだったから毎日顔を合わせていたんだけど、
中途半端に恋心を自覚しちゃったせいか昔みたいに気兼ねなく話せなくってね。
丁度その頃から巫女としての訓練も忙しくなってきて……
それを言い訳にアイツと少し距離を置いてたんだ」
女の人は「馬鹿だよねー」と小さく呟く。
その一瞬だけまた寂しそうな顔になる。
なんでだろう、妙にその表情が気になる。
「そのままあっという間に高校卒業。しかも、アイツは県外の大学に行っちゃってね。
あっちに行く日に頑張って告白しようとしたんだけど……やっぱりできなくて。
大学を卒業したら戻ってくるかなーって思ってたんだけど、
気付いたらそのままあっちで就職しちゃっててさ。
そのままアイツはずーっと向こうにいて何の音沙汰もなし。
まあアチコチを転々としてたらしいから忙しくて連絡が取れなかったんだろうねえ」
女の人はそこでいったん話を区切り、こちらをチラッと見る。
その目はぼくのほうを向いていたけれども、
ぼくの頭よりもちょっと高いぐらいの辺りを見つめていた。
「そんなアイツから、久しぶりにに連絡があったのが1年前。
仕事が一段落したから帰省するっていう連絡がアイツのお母さんにあったんだ。。
嬉しかった、アイツはまだ私を気にしてくれてるんだって分かったから。
ワクワクしてアイツが帰ってくるのを待ってたよ……あの電話がかかってくるまでは」
女の人はそこで少しだけ深呼吸した。
ぼくは女の人がこれから大変なことを話すんだと感じて、少し背筋を伸ばす。
そして、女の人はまた話し始めた。
「その日は昼にアイツから電話がかかってきて、久しぶりに色々話したんだ。
大学に行ってからのこととか、こっちの村のこととか……
そんなに話してる時間もなかったみたいですぐに切れちゃったけど、
次の日には帰ってくるって言ってたからその日は安心していたのに。
次の日の夜になってもアイツは帰ってこなかった。
私とアイツのお母さんで夕方頃まで待っていたけど全然連絡がなくて……
それで、夜になってからアイツのお母さんが真っ青な顔を涙でクシャクシャにして、
アイツのお父さんと一緒にうちに、来たの……
それで、アイツが事故で……ぐすっ、電車に轢かれたって、聞いて……」
女の人はそのまま静かに嗚咽を漏らす。
ぼくはただその様子を黙ってみていることしかできなかった。
しばらくそうしていたけど、少し泣いたら落ち着いたみたいだった。
「ごめんね、まだ思い出すたびに、悲しくなっちゃって……」
そう言ってアハハと笑う。
けど、やっぱり最初に笑ってた時とちがってどこか寂しそうな顔だった。
その顔を見て、胸の奥の方でチクリと何かに刺されたような痛みが生まれた。
どうしてこんなにも悲しいんだろう?
「こんな話聞かせちゃってごめんね」
「でもどうしても聞いて欲しかったんだ……私の、初恋の話を……」
そう言って女の人は、ぼくから目を逸らして立ち上がる。
「……っ……スンッ……あ、そういえば」
女の人が唐突に声を上げ、巫女装束のあちこちをゴソゴソと探り出す。
しばらく何かを探していたようだったけど、
やがて見つかったのか懐から何かを取り出した。
「はい、これ持っててね」
そう言って女の人は木で出来た指輪のような物を手渡してきた。
「怖い奴らからキミを護ってくれる物だから、山に行くまでなくしちゃ駄目だよ」
女の人はその木の指輪みたいなものに紐を通して、ぼくの首にかける。
紐が簡単にほどけないかを確認し終えた女の人は一つ頷くと、
そのまま境内へと降りていった。
そしてその場でキョロキョロと辺りを見回し始める。
誰か探しているのかな……?
ぼくはしばらくその様子をじっと見ていたけど、
ふとあることを思い出してお尻のポケットの中をゴソゴソと漁る。
目的のものを見つけたぼくは、女の人が戻ってくる前に賽銭箱の中にそれを放り込む。
小石とかとちがって怒られはしない、はず。たぶん。
そんな風に少しだけドキドキしていると、女の人がこっちへ戻ってくる。
太陽はもう殆ど山の向こうに隠れてしまって、辺りはどんどん暗くなってきていた。
そろそろ帰らないとまずいかな。
「おーい、お待たせ!」
女の人にそろそろ帰ると伝えようとしたとき、
裏山へ続く道の方から声が聞こえてきた。
ぼくと女の人がそちらに目を向けると、あの子とお婆ちゃんが歩いてくるのが見えた。
「ああ……良かった、間に合いましたか……」
「ごめんごめん、お婆ちゃん案内してたら遅くなっちゃって」
「いえ、まあ、色々話ができたから……良かったです、けど、も……」
「そっか、そりゃぁ良かったよ」
あの子と女の人が話しているのを見ながら、ぼくはお婆ちゃんの方に歩いていく。
お婆ちゃんはぼくが近くに来ると頭の上に手を置いてなで始める。
「ごめんねぇ、遅くなっちゃって」
「ううん、そんなに待ってないよ」
「そうかい、そうかい、それは良かった……どうだい、楽しかったかい」
「うん、楽しかった! でももうちょっと遊んでいたかったな……」
「だいじょうぶ、これからはずっと近くに居られるし、
来年になればまた逢えるからねぇ」
「そうなんだ」
「だからほら、今日はもうかえろうや」
「はーい」
ぼくとお婆ちゃんは女の人たちの方を見ると、
あの子がぼくたちの視線に気付いて女の人を促した。
「道中に気をつけて……還ってくださいね」
「ま、道中はこの子がしっかり清めといたし、
魔除けも持っているから大丈夫だと思うよ」
二人はそう言って微笑む。
ぼくとお婆ちゃんはそんな二人に向かって頭を下げる。
顔を上げるとあの子が手を小さく振ってバイバイしていた。
その様子を見ながら、ぼくはお婆ちゃんと手を繋いで裏山の方へ歩いていく。
その途中、もう一度振り返ると女の人と目が合った。
女の人は一瞬ビクッとしたけど、あの子に小突かれてハッとする。
「また来年、絶対にね!」
そう言ってブンブンと大きく手を振ってくる。
あの子が女の人の隣でその様子に苦笑している。
ぼくは少し恥ずかしかったけど手を振り返し……
(またね!)
と、心の中で大きく叫んだ。
その声が聞こえたのか分からないけど、
より一層強く振られ始めた手を見ながらぼくは神社を後にした。
―夕暮れの中の神社
小さくゆらゆらと揺らめく背中が二つ、夜闇が濃くなりつつある山へと消えていく。
その背中が見えなっても、私はしばらく涙を流しながら手を振り続けていた。
「やーれやれ、なんとか無事に逝ってくれたか」
私の隣に座って、あぐらをかいている少女がボヤく。
先程まで白いワンピースに麦わら帽子を被っていた姿だったはずだが、
気が付けば紅葉の模様が鮮やかな紅い和服を着ていた。
彼の祖母を連れて来た時には年相応に見えたその顔には、
仕事をやり遂げた後のサラリーマンの様な疲れた表情が浮かんでいる。
この少女は、もちろん見た目通りの年ではないし、そもそも人ですらない。
この村で祀られている神様であり、名を『御縁様』という。
「いやー、今回はホントもう駄目かと思ったけど意外となんとかなるもんだねぇ」
非常にまじめな話をしているはずなのだが、
麦茶をゴクゴクと喉を鳴らしながら飲んで、
パタパタと団扇を煽ぐその姿からはそんな気配など全く感じ取れない。
「そんなに、大変だったんですか?」
目元に残っていた涙を拭いながら、私は御縁様に言葉を返す。
御縁様は残っていた麦茶をグイーっと呷り、
私の方にぐるっと体ごと振り向いた。
「1年も前の霊体だったんだ、あっちこっちスリ切れて、
いつ消えてもおかしくなかったよ」
ゆらゆらと揺らぐ輪郭、帰ることしか考えられない単純さ。
そして、刻々と小さくなっていく身体と精神。
彼はその存在を保てなくなる一歩手前だった。
そう、御縁様は私に説明してくれた。
「1年間も自縛霊をやっていたんだ、今の今まで残っていたのが奇跡ってもんだよ」
彼が死んでから約1年間。
怨念に塗れた悪霊ならいざ知らず、
ただの自縛霊がそこまで長く現世に留まっていられたのがそもそも奇跡的なのだ。
「まぁ、現世によっぽど強い執着心があったんだろうね」
「執着心、ですか……?」
「どうしても成功させたい仕事があるとか、どこかの大会で優勝したいとか。
負の方面で言えば、上司を怨んでいるとか、別れた恋人に未練があったりとか。
……そして、告白できなかった幼馴染のことが気になって仕方がなかった、とかね」
「……ぁ」
「やーれやれ、そんな顔をするんじゃないよ……まったく」
私が再び泣きだしたのを見て、
御縁様は自身の懐から取り出したハンカチを私に投げて寄越す。
……そんなこと言われても自然と涙が零れてくるのだからどうしようもない。
私はそれを受け取り、とめどなく流れる涙を拭う。
ようやく涙が止まる頃にはハンカチには大きな染みできていた。
私はその涙でぬれたハンカチを懐に仕舞う。
御前様はそんな私を見て「ニヒッヒッヒ……」と意地の悪い声を漏らす。
……このハンカチはさっさと洗って返そう。そう心に誓う。
そして、どうしても聞きたかったことを御縁様に尋ねてみる。
「あの、御縁様」
「なんだい?」
「1年も自縛霊をしていたアイツが帰って来られたのは、どうしてなんでしょう」
そう、もしいつでも帰って来ることが出来たのならば、
事故にあった1年前に帰って来ている筈なのだ。
それが1年越しになった理由……私はそれが気になって仕方がなかった。
「さぁ?」
「『さぁ?』って、ちょっと!?」
相も変わらず小馬鹿にしたような笑みを浮かべながら御縁様が答える。
私は腰を浮かせて食って掛かろうとしたが、
それよりも早く御縁様が言葉を重ねてきた。
「いやいや、別に馬鹿にしているわけじゃないんだよ。
ただ今回は本当に突然縁が戻ったからね、私にも分からないのさ」
そう言って御縁様は手に持ったままだった麦茶のコップをやや強めに床に置く。
その淀みない言葉と、落ち着けと言わんばかりの動作に私はハッとし、
勢いよく浮かせていた腰をゆっくりと降ろした。
「去年亡くなった時には彼の手には私と縁を繋ぐための御守りがなかった。
それがどういうわけか今日になって彼の元に戻ってきた……ということなんだろう。
どういう理由で戻ってきたのかなんて、その場に居なかった私には分からんよ」
そういって御縁様は肩を竦める。
そういえば、確かに送られてきた彼の遺品の中に御守りはなかった。
他にもいくつか足りていない物があったらしいので、
恐らく跳ねられた時に紛失したんだろうと警察の人は言っていた。
それが今日、お盆の最終日に偶然彼の手に戻った……?
「もしかしたら向こうの土地神が気を利かせてくれたのかもしれんなー」
「むこうの土地の、土地神様が、ですか」
「縁を通して何度かあっちへ行った時に挨拶に行ったんだが、
地物や酒を交換しているうちに仲良くなってしまってなあ。
彼についても色々と融通を利かせといてくれるようにお願いしておいたんだよ」
そう言ってお茶うけのどら焼きを頬張る御縁様。
満面の笑みを浮かべながら食べるその姿は年相応に見えるし、
時々喉に詰まらせてはお茶を飲んでいる様子からは威厳などまったく感じられない。
それにしても神様同士の縁ってなんだか不思議な感じだなー。
八百万の神様って一括りにされる事が多いから皆顔見知りなのかと思っていたけれど、
もしかしたら私が思っているよりも神様同士の関係は難しいのかもしれない。
「しかしまあ、流石に今日は疲れたから大人しく山に還るとするよ」
「お疲れ様でした……次はいつ降りて来られるんですか?」
「んー、次は月が代わる頃に降りてくると思うから宜しくねー」
そういって御縁様は社殿の中へと入ろうとする。
しかし、その寸前で何かを思い出したのか、足を止めてこちらを振り返る。
「あー、そういえば賽銭箱になんか入ってるから開けて見といてね」
御縁様はそれだけ言い残すとサッサと社殿の中に入って行った。
私が賽銭箱から視線外してチラッと中を覗いた時には、
すでにその姿は社殿内から消えていた。
神社の中の神棚から山の神棚へ移動しているだけだと説明されたことがあったが、
正直言って何を言っているのかサッパリ分からなかった。
こんなんだから馬鹿巫女と言われるんだろうなー……
そんな風に考えながら、私は持ってきた麦茶のグラスとお盆を片付け始める。
お盆の上にコップとお茶うけの皿を乗せ、両手で持って立ち上がる。
その時、チラッと賽銭箱が目の端に映った。
そういえば、何か入ってるって言ってたな……
御縁様の言葉が気になった私は持ち上げたお盆を下ろし、
賽銭箱の鍵を開けて中を覗きこむ。
まばらに入っている小銭の中に一つだけ違う物が紛れていた。
私はソレを取り出し、掌の上に載せる。
これは……御守り?
先程のご縁様との会話を思い出してハッとする。
もしかしてこれはアイツの御守りなんじゃ……!?
私はその御守りもお盆の上に載せると、急いで母屋へと向かった。
台所でコップを洗ってお盆と団扇を片付けると、
階段を勢いよく登って2階の自室へと向かう。
自室に入って後ろ手にドアを閉めた私はそこで一息つくと、
部屋の真ん中にある炬燵机の前に座って読書灯をつける。
そして、手に持っていた御守りを机の上にそっと乗せた。
じぃっとよく見てみると、あちこち擦り切れていてボロボロになっている。
その擦り切れてボロボロになった部分を通して、
便箋のような物が入っていることに私は気付いた。
私は誰も居ないのにキョロキョロと辺りを見回し、
それからゆっくりと袋の口を開けて中身を取り出した。
便箋はヨレヨレになっていて、何度も読み返されたのだと分かる。
震える手で便箋を開いて中を確認すると、
少し擦れ気味のアイツの文字が目に飛び込んできた。
私はその文字をゆっくりと指でなぞる。
一度、二度……なぞる度に文字がボヤけて見え辛くなっていく。
いけない、これじゃいつまで経っても書いてある内容が読めない……
私は便箋から指を離すと、懐からハンカチを取り出して涙を拭く。
そしてもう一度便箋に目を落とし、その内容を読み始めた。
『― 深山白夢へ
ずっと昔から、それこそ小学校の頃から好きだった。
女々しいとクラスの男子からかわれていた私を庇ってくれた時は本当に嬉しかった。
あの時は恥ずかしくて言えなかったけど、ずっとありがとうって言いたかった。
中学校に上がってからは恥ずかしくなって部活に没頭していたけれども、
朝早く境内を掃除している姿や、校舎から出て行く姿を見るたびにドキドキしてた。
高校に行ってからは恥ずかしさから距離をとることはなくなったけど、
どういう関係になりたいのかが良く分かっていなくて結局疎遠になってしまった。
その時にはもう、君のことが好きだってことに気付いていたんだけどね。
そして大学に行く今、ようやく心が決まった。
遅すぎるかもしれないけど、考えた末に決めました。
こんな私と、どうか付き合ってください。
―桜庭圭介より』
ここまで読んで、私は便箋から目を離す。
これで何度目だろう。私の目からは再び涙が零れ落ちていた。
あー……私も、アイツも馬鹿だ。大馬鹿だ。
これじゃあ、御縁様に馬鹿って言われても仕方ないなあ。
泣きながらアハハ……と乾いた笑い声を上げる。
両思いだったんだ。なのにどっちも告白しないでさ、そのまま……そのまま……
もう、溢れる涙を止めることはできなかった。
私はしばらくの間、御縁様から借りたハンカチに大きな染みを作り続けた。
ようやく落ち付いた頃には時計は0時少し前を指していた。
ぜんぜん眠れる気はしなかったけれど、片付けぐらいは済ませておこう……
そう思って便箋を片付けようとした時、私は最後の方に書かれた走り書きに気がついた。
その走り書きは本文よりもしっかりしており、後から継ぎ足された物だと分かる。
私は涙で腫れた目でその走り書きを読んだ。
『 来週帰郷
宝石店受取り 水1600
MIYAMA KEISUKE, MIYAMA HAKUMU
絶対に渡す』
宝石店受取り? 書類?
いったい何のことなんだろう、ただのメモ?
少し考えても良く分からなかったのでとりあえず放っておくことにする。
私は便箋をもう一度きれいに折り畳むと、御守りの中に入れようとする。
その時になって、私は御守りの中にもう一つ別の物が入っていることに気付いた。
紙に包まれたソレを取り出し、窓から差し込む月明かりに中身をかざす。
それは、指輪だった。
月の光を反射してキラキラと銀色に輝いていて、
まるでお伽噺に出てくる魔法の指輪みたいだった。
内側には『MIYAMA HAKUMU』と文字が彫られている。
それは、結婚指輪だった。
私は、ぼうっと指輪を見つめていた。
先程のように泣くでもなく、ただ静かに指輪を見ていた。
そして……
夢見心地のまま、
その指輪を左手の薬指に嵌めて……
チリーン……
小さく、風鈴の音がした。
その音で私は目を覚ます。
時計を見てみると深夜の0時だった。
私は慌てて部屋の窓を開け、御山の方を見やる。
すると、御山のてっぺんに沢山の光の玉が集まっているのが見えた。
その光の玉達は、まるで何かに導かれる様に天へと昇っていく。
ひとつ、ふたつ、みっつ……
光の玉が空に舞う様子はさながら蛍の群れのようでもあった。
気付けば光の玉は殆ど飛びさり、残すは2つだけとなっていた。
私にはそれが、アイツ……圭介なんだって分かった。
そう思った瞬間、あの光の玉がこっちを向いた気がして、
無意識にその光に向かって左手をゆっくりと振る。
すると光の玉は一瞬だけその光を輝かせると、
もう一つの光の玉と共にゆっくりと空へと昇っていく。
私は左手を振りながらその様子を静かに見ながら、
小さい頃に御婆ちゃんから聞かされたお話を思い出す。
毎年一回、お盆の日。
御縁様に縁のある魂達は、御縁様に連れられて御山から天へと還る。
そして、また次の年のお盆に御山へと還り、村の人々と触れ合う……
この村に代々伝わる『御霊還り』の伝承であり、
今でも続く大切な神事でもある。
そして圭介が御山へと還っていったということは、
四季が巡り続ける限りこの地でまた逢えるということ。
10年後、20年後、30年後であっても同様に逢うことができる。
だから、別れの言葉は必要ない。ただ一言、こう言えばいい。
「またね」
と。
私は大きく伸びをして寝る準備を整える。
明日のお仕事は何があったかなー……
なんてことを考えながら布団に潜りこみ、数十秒後には寝息を立て始める。
……月明かりに浮かぶその顔はとても穏やかで、そして幸せそうであった。
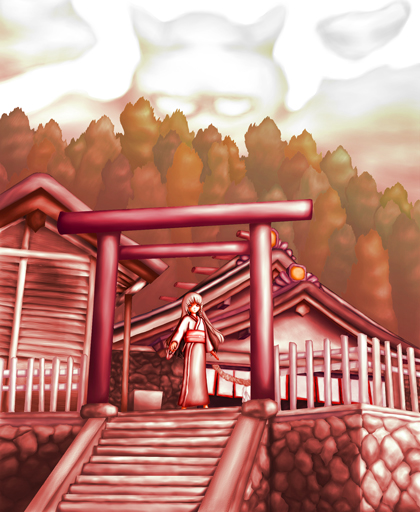 <イラスト:夕焼けの中の神社と御縁様>
『ある夏の日の里がえり』 おわり
<イラスト:夕焼けの中の神社と御縁様>
『ある夏の日の里がえり』 おわり
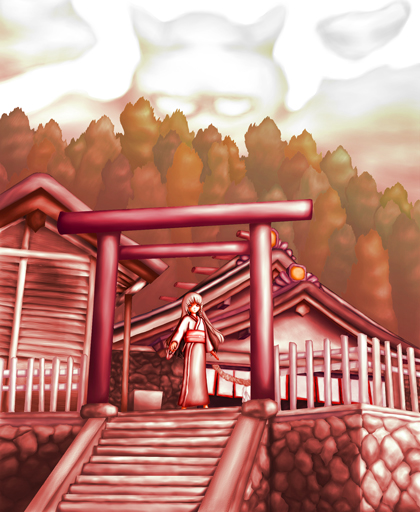 <イラスト:夕焼けの中の神社と御縁様>
『ある夏の日の里がえり』 おわり
<イラスト:夕焼けの中の神社と御縁様>
『ある夏の日の里がえり』 おわり

感想・拍手を送って頂けましたら幸いです。
(WEB拍手です。Created by 香月清人様)